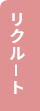各種指針
天心堂おおの訪問看護ステーションでは、安心・安全なサービス提供のために、運営規程や各種指針を定めています。本ページでは、虐待防止、感染症対策、ハラスメント防止に関する基本方針をご覧いただけます。
天心堂おおの訪問看護ステーション運営規程
(事業の目的)
第1条
この規程は、社会医療法人財団天心堂が設置する天心堂おおの訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員
及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防
訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を
確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
- ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
- ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
- ステーションは事業の運営にあたって、関係市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条
- ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
- ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
- 名 称:天心堂おおの訪問看護ステーション
- 所在地:大分県豊後大野市大野町田中2番地の9
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
- 管理者:看護師若しくは保健師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、 当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 - 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。 - 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: 適当数 ※必要に応じて雇用する 看護職員の代わりに、看護業務の一貫としてのリハビリテーションを担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条
ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
- 営業日:月曜日から土曜日まで 但し、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。
- 営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。(土曜日は12時30分まで)
- 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条
居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。ただし、医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
- 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
- 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条
訪問看護の内容は次のとおりとする。
- 療養上の世話
清拭・入浴介助などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア - 診療の補助
褥瘡の予防・処置、点滴、創傷処置、カテーテル管理等の医療処置 - リハビリテーションに関すること。
- 家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(緊急時における対応方法)
第10条
- 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
- 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条
- ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又当該事業が法定受領サービスである場合は3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
- ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置
(2) 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。一 1キロメートル当たり 33円
(通常の事業の実施地域)
第12条
通常の事業の実施地域は、豊後大野市とする。ただし、事業所より16キロ範囲内とする。
(相談・苦情対応)
第13条
- ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
- ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
(事故処理)
第14条
- ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
- ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
- ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条
- ステーションは、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的(年2回以上)に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底する。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年1回)に実施する。
(4)前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(5)利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備する。 - ステーションは、指定訪問看護の提供中に、看護師等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の原則禁止)
第16条
- ステーションは、指定訪問看護の提供にあたっては、該当利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わない。
- ステーションは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の理由、内容、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(個人情報の保護)
第17条
- 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
- ステーションが得た利用者又はその家族の個人情報については、ステーションでの介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(その他運営についての留意事項)
第18条
- ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後6ヶ月以内の初任研修
(2) 年2回の業務研修 - 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
- ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)
附 則
この規程は、令和3年12月1日から施行する
令和3年3月1日改定
令和6年4月1日改定
高齢者虐待防止のための指針
1.虐待の防止に関する基本的な考え方
高齢者に対する虐待は、高齢者の尊厳を脅かす深刻な事態であり、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)に示すとおり、その防止に努めることは極めて重要である。
当事業所では、同法の趣旨を踏まえ、また介護保険法が掲げる「尊厳の保持と自立支援」という目的を達成し、当事業所が掲げる理念「ご利用者様が安心して住み慣れた環境で療養生活を継続できるように、計画的に看護サービスを提供する」を実現させるため、虐待の未然防止、早期発見、迅速かつ適切な対応等に努めるとともに、虐待が発生した場合には適正に対処し再発防止策を講じる。そのための具体的な組織体制、取組内容等について、本指針に定める。
2.高齢者虐待の定義
1)「高齢者」とは、65歳以上の者をいう
2)「高齢者虐待」とは、①養護者による虐待、②養介護施設従事者等による虐待をいう
3)高齢者虐待の類型
- 身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。(蹴る、殴る、たばこを押し付ける、熱湯を飲ませる、食べられないものを食べさせる、食事を与えない、戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、紐などで縛る等) - 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。(性交、性的暴力、性的行為の強要、性的雑誌や DVD を見るように強いる、裸の写真や映像を撮る等) - 心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しい拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外 傷を与える言動を行うこと。(「そんなことをすると外出させない」など 言葉による脅迫、「何度言えばわかるの」など心を傷つけることを繰り返す。成人の利用者を子供扱いするなど自尊心を傷つける、馬鹿にする、無視する、他者と差別的な対応をする等) - ネグレクト
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置。利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。(自己決定と言って放置する、失禁していても衣類を取り替えない、栄養不良のまま放置、病気の看護を怠る、話しかけられても無視する、拒否的態度を示す等) - 経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。 (利用者の同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分)
3.高齢者虐待の定義
虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務等虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり「虐待防止委員会(以下「委員会」という)を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じる。
- 委員会の名称は「虐待防止委員会」とする
- 委員会の委員長は、管理者が務める
- 委員会の委員は、委員長が法人内より 4~5 人程度選出する
- 委員会は、6ヶ月に1回以上の間隔で定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催する。
- 委員会の審議事項
(1) 基本理念、行動規範等、職員への周知に関すること
(2) 職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること
(3) 職員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること
(4) 虐待防止、早期発見等に向けた取り組みに関すること
(5) 苦情解決制度、第三者評価、成年後見制度の活用に関すること
(6) 虐待発見時の対応に関すること
(7) その他人権侵害、虐待防止に関すること
(8) 虐待の防止のための指針の整備、見直しに関すること - 委員会内容の周知徹底
委員会での検討内容及び決定事項については議事録を作成し回覧する。
【委員会構成員ごとの役割】
| 構成員 | 役割 |
|---|---|
| おおの事業体 管理者 | 委員長(責任者) 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者 |
| おおの事業体 事務長 |
副委員長 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者 |
| 看護師長 | 虐待防止措置の周知、進捗管理 |
| 看護職員等 | 医療的ケアに関する検討、医師召集の要否検討 |
| 各課長 | 利用者・家族等への説明、相談対応 |
4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止、早期発見と発生時の速やかな被虐待者保護を実務化するため、全職員に定期的な研修(年1回以上)を実施するものとする。職員の新規採用時にも実施する。研修内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止の徹底を行うものとする。研修実施内容は、都度委員会において記録し保管する。
5.虐待防止に関する責務等
- 虐待防止に関する統括は介護事業部統括管理者が行い責任者は管理者とする。
- 虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図ると共に、成年後見制度の利用支援、苦情解決体制の活用など日常的な虐待の防止等の取り組みを推進する。また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
【相談窓口】
豊後大野市地域包括支援センター 電話番号0974-22-0505
豊後大野市高齢者福祉課
〔在宅高齢者〕いきいき高齢者係 電話番号0974-22-1048 内線2173
〔施設入所者〕介護保険係 電話番号0974-22-1076 内線2176
(1)成年後見制度の利用支援に関する事項
虐待等の防止の観点を含めて、成年後見制度その他の権利擁護事業について、利用者や家族等へ説明を行う。また、擁護者による虐待が疑われる場合等においては、委員会が直接各区役所等に連絡し、対応について相談する。
成年後見支援センター(豊後大野市社会福祉協議会) 電話番号0974-22-6677
(2)虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待等に係る苦情については、重要事項説明書に示す、当事業所において包括的に設置する苦情対応窓口において受け付ける。受付担当者は苦情等の内容を精査し、虐待等に関係する内容が含まれている場合には、苦情対応責任者を通じて、委員会に報告する。
6.虐待の早期発見等への対応
- 虐待の早期発見
虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、速やかに責任者等へ報告する。なお、虐待は利用者の権利侵害する些細な行為から虐待へとエスカレートする傾向にあることを認識し、平素から責任者等は、利用者、家族、職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努める。 - 虐待発見時の早期対応
虐待もしくは、虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全、安心の確保を最優先とし、利用者や家族に誠意ある対応や説明をする。また、被害者のプライバシー保護を大前提としながらも、対外的な説明責任を果たすことなど、速やかに組織的な対応を図る。また、行政に通報、相談することとする。さらには、発生要因を十分に調査、分析するとともに、再発防止に向けて、組織体制の強化、職員の意識啓発等について、一層の徹底を図ることに努めることとする。
7.本指針の閲覧
本指針は、利用者、家族(身元引受人等)、後見人等の関係者及び当事業所職員、ならびにその他関係者がいつでも閲覧できるよう、事業所内に常設されている虐待防止マニュアルと共に保管し自由に閲覧可能とします。当施設のホームページでも公表し、利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。
附則 本指針は 2023 年2 月 1 日より施行する。
感染症の予防及びまん延防止のための指針
1.基本方針
天心堂おおの訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)は、利用者の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に感染の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
2.事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための考え方
事業所は感染症の予防及びまん延の防止のため、以下の事項について職員に周知徹底を行う。
- 感染症対策についての基礎知識を理解することができる
- 標準予防策(スタンダードプリコーション)の実施に努める
- 介護・看護ケアで感染を予防する為に、手指衛生(手洗いと手指消毒)を徹底する
- 地域でどのような感染症が流行しているか把握し、必要な感染症予防対策を実施する
- 職員は日々の健康管理を徹底し、職員の健康を守ることに努める
3.基本対応
- 平常時の対策
(1)事業所内の衛生管理(環境整備等)
・人がよく触れる場所、訪問車内、訪問の使用物品について除菌クロスで拭く
・換気を行う(事業所内・車内)
・ゴーグル、マスク、手袋、エプロンなど物品管理
(2)ケアにかかる感染対策(手洗い、標準予防策)
・出勤前の検温、体調管理(体調不良時の早期報告、出勤停止)
・出退勤時の手洗い、手指消毒
・利用者及び家族の健康状態の把握
・勤務中のマスク着用、利用者へマスク着用の呼びかけ
・職員の標準予防策の徹底、手指衛生のタイミング順守
・感染の可能性がある場合は、荷物は最小限にして玄関でPPE 装着する
・血液・体液・排泄物等の処理方法の徹底
- 感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1)発生状況の把握
(2)感染拡大の防止
(3)医療措置
(4)区市町村への報告
(5)保健所及び医療機関との連携
※報告や連絡の体制は感染対策マニュアルに基づいて行う
4.感染対策委員会の設置
事業所での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族などへの適切な対応を行うため、感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 事業所における感染対策責任者は管理者とする。
【委員会構成員ごとの役割】
役割 担当者 施設全体の管理 施設長 感染対策委員会実施のための各所への連絡と調整 事務長 医療・治療面の専門的知識の提供 医師 感染対策担当者
医療の提供と感染対策の立案・指導
利用者、職員の健康状態の把握看護職員 支援現場における感染対策の実施状況の把握
感染対策方法の現場への周知生活支援員 食事の提供状況の把握
利用者の栄養状態の把握管理栄養士 - 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
- 委員会は定期的(3ヶ月に1回)かつ必要な場合に担当者が招集する。
- 委員会の議題は、担当者が決める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。
(1)事業所内感染対策の立案
(2)指針・マニュアル等の整備・更新
(3)利用者及び従業者の健康状態の把握
(4)感染症発生時の措置(対応・報告)
(5)研修・教育計画の策定及び実施
(6)感染症対策実施状況の把握及び評価
5.従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次ぎのとおり実施する。
- 新採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。 - 定期的研修
感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。 - 訓練(シミュレーション)
事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
6.本指針の閲覧
本指針は、利用者、家族(身元引受人等)、後見人等の関係者及び当事業所職員、ならびにその他関係者がいつでも閲覧できるよう、事業所内に常設されている感染対策マニュアルと共に保管し自由に閲覧可能とします。当施設のホームページでも公表し、利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。
附則 本指針は、令和6年2月1日から施行する。
ハラスメント防止のための指針
1.基本的な考え方
天心堂おおの訪問看護ステーションは、利用者に対してより良い介護サービスを提供できる環境を確保するとともに、職場及び介護の現場におけるハラスメントを防止するために、本指針を定める。
2.ハラスメントの定義
- 職場内におけるハラスメント
(1)セクシャルハラスメント
職場において、性的な関心や欲求に基づく言動や性別・性的指向・性自認に関する偏見等に基づく言動によって不快又は不利益を与え、職場環境が害される行為で、下記のようなものをいう。
①性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報や噂等を流布 すること、性的な冗談やからかい、性に関する偏見に基づく発言、個人的な性的体験談を話すこと等)
②性的な行動(性的な関係を強要すること、性的な内容の電話、手紙、メール等を送ること、身体に不必要に接触すること、食事やデートに執拗に誘うこと、性別の偏見により職務内容を決めること、酒席でのお酌やデュエット等の強要等)
(2)パワーハラスメント
職場において、職務上の地位等の優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害される行為で、下記のようなものをいう。
①身体的な攻撃(暴行・障害等)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等)
③人間関係の切り離し(隔離・仲間はずれ・無視等)
④過少な要求(仕事の抑制・能力とかけ離れた程度の低い職務の命令等)
⑤過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害等)
⑥個の侵害(プライベートへの過度な立入り等)
(3) 妊娠、出産、育児、介護等に起因するハラスメント
職場において、妊娠・出産や育児・介護にかかる休業等の利用に関する言動により、妊娠、出産、育児、介護等の当事者である職員の職場環境が害される行為をいう。 - 介護現場におけるハラスメント
(1)その他のハラスメント(カスタマーハラスメントを含む)
利用者・家族等から職員への行為、職員から利用者・家族等への行為で、下記のような行為をいう。
①身体的暴力(ものを投げる、叩く、蹴る、唾を吐く等、身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
②精神的暴力(大声で威圧する、どなる、理不尽な要求、暴言等、個人の尊厳や人格を言葉や態度で傷つけたり、おとしめたりする行為)
③セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘い掛け、好意的態度の要求、性的な嫌がらせ行為)
3.職場内におけるハラスメント対策
- 職員の責務
(1)ハラスメントの禁止
全ての職員は、ハラスメントについて正しく理解し、ハラスメントを行ってはならない。職場の一員であることを自覚し、円滑なコミュニケーションを心掛け、より良い職場環境づくりに努める。
(2)ハラスメントへの対応
職場でハラスメントを受けた場合又は発見した場合は、管理者に相談する。
(3)研修会
ハラスメント防止のために、年1回は本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。 - 管理者の責務
(1)職場環境の整備
管理者は、職員間のコミュニケーションが図られ、職員一人ひとりがその能力を十分に発揮できるよう、風通しの良い職場環境を確保できるよう努めなければならない。
(2)苦情・相談への対応
管理者は、職員からハラスメントに関する苦情・相談があった場合には、迅速かつ適切に対応する。
(3)職員の意識啓発の推進
管理者は、職員がハラスメントについて正しく理解し、ハラスメントの未然防止を図るため、本指針の周知に努め、職員の意識や職場の実態を把握するとともに、職員に対するハラスメント防止研修を実施する。